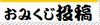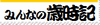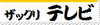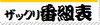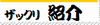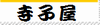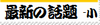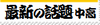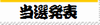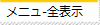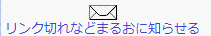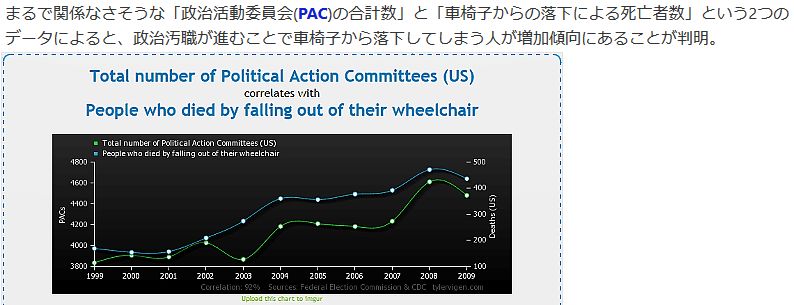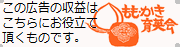gakushu - 最新エントリー
(NHK20140416)
1931年4月、石原莞爾 著
「現在の将来に於ける日本の国防」文書:
我らが支那中心の戦争を準備せんと欲せば
東亜に加わり得ヘき凡ての武力(英米ソ)
に対する覚悟を要ス」
1936年8月、
石原莞爾「対ソ戦争指導計画大綱」策定:
英米の中立を維持せしむる為にも
支那との開戦を避けること極めて緊要なり。
(支那と開戦すれば英米の干渉は必至である)
(NHK20140602)
市民科学者、高木仁三郎
(NHK20151023)
スターリンは昭和13年(1938年)2月、
日中戦争に深入りを始めた日本を評して、
「歴史はふざけることが好きだ。ときには
歴史の進行を追い立てる鞭(むち)として、
間抜けを選ぶ」と述べ、早くも
ソ連や米国の対日戦勝を予期していた。
(JBpress 2020.07.27)
(NHK20141023)
(NHK20131014)
南フランス・ニースの郷土料理、ソッカ
(NHK20181014)
「真実はいつもひとつ」のはずですが、
真実を確かめるために実験したとしても、
必ず1つの結果が得られるわけではありません。

「薬の効果は偶然ではない」と統計学的に判断できたとき、
その結果を「有意」と呼びます。しかし、この「有意」という
言葉に振り回されていると科学者800人が反対意見を表明しています(2019/03/20)。
1925、ロナルド・フィッシャーは有意差検定という手法を開発。
例えば、実験結果が起こりえる確率が95%以上である場合は、
慣例的に科学者は「起こりえる確率は95%以上ならば、
この実験結果は偶然ではない」と判断し、「有意である」
としていました。
当初、「有意であるかどうか」は
「この実験結果は95%以上の確率で起こりえる」
ということを示しているだけのはずでしたが、次第に
「有意かどうか」が研究結果の結論を左右するようになり、
「研究が発表されるかどうか」や
「実験が助成金を受けられるかどうか」などまで
支配するようになっているとのこと。
アメリカ統計学協会事務局長ロン・ワッサースタイン氏:
「実験結果を改ざんして、P値を自分の望む数値に
近づける研究者や、実験に意義がある場合でも
有意ではないために実験結果を公表しない研究者もいる」
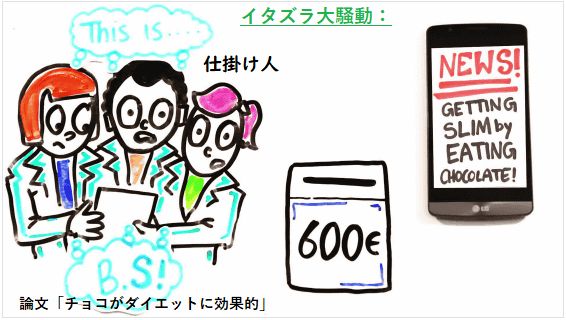
詳細→YouTube:AsapSCIENCE
(NHK20140419)
(NHK20180118)